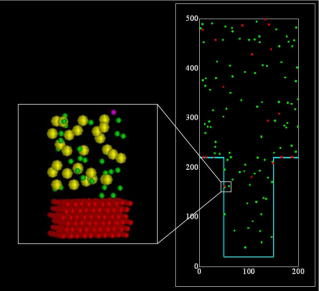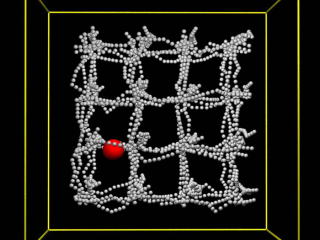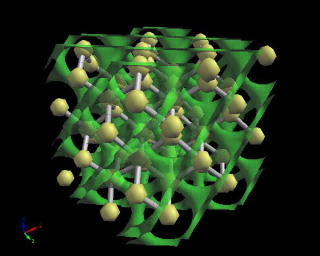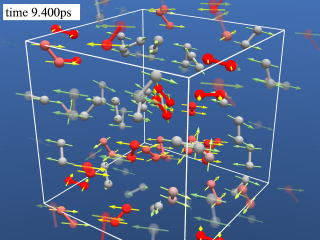■計算物性研究室の歩み (第一期:1966年頃) 山崎 正利 教授 素粒子論及び一般性相対理論、 木村 実 助教授 場の理論,固体物理学及び 樋渡 保秋 助手 統計力学の基礎 (第二期:1989年〜) 山崎 正利 教授 木村 実 教授 上記(第一期)に加え計算物理学 樋渡 保秋 教授 高須 昌子 助手 (第三期:1995年〜) 樋渡 保秋 教授 上記(第二期)に加え第一原理計算 高須 昌子 助教授 スタッフの所属は1996年4月に 小田 竜樹 助手 物理学科から計算科学科へ移る (第四期:1999年〜) 樋渡 保秋 教授 高須 昌子 助教授 上記(第三期)とほぼ同じ 小田 竜樹 講師 (第五期:2004年〜) 樋渡 保秋 教授 (2006年3月退官) 斎藤 峯雄 教授 高須 昌子 助教授 上記(第四期)に加え半導体物理、 小田 竜樹 講師 QMD(量子分子動力学)など (第六期:2006年〜2009) 斎藤 峯雄 教授 高須 昌子 助教授 上記(第五期)に加え 小田 竜樹 助教授 マテリアルデザイン 石井 史之 助手 (第七期:2009年〜2011) 斎藤 峯雄 教授 小田 竜樹 准教授 高須 昌子准教授が、 石井 史之 助教 東京薬科大学・生命科学部の教授に転任した。 (第八期:2012年〜) 斎藤 峯雄 教授 石井 史之 准教授 石井 史之氏が准教授となる。 固体物理学の電子状態計算手法を用いる 半導体、磁性体、超伝導体、カーボン新材料などの 物性のデザインに関する研究
|